2024年09月23日
「走れメロス」(8)終了後雑感
作品雑感「走れメロス」(1)・(7)当日用資料
「走れメロス」(8)終了後雑感
[上演を終えて]
メロス2days、思った以上にしっかり手応えあって終えています。まあ案の定、体力の衰えは隠しきれずでしたけど、リハで指摘いただいたように、それがむしろメロスの体のというより、気持ちの強さにつながってくれたみたい。
さすがに釧路での立ちきれずの転倒はよろしくなかったけど(後述)、そういう状態になることを見越した動きは開発できると思う。
//
まずは札幌。いい具合に広さ使えて、方向とか主客スタンスに大きなミスなく手応えあったわ。
そしてどうやら事前に想定していた「メロス降りてくる」タイプの作品では、今回はなくなってたのが分かった。メロスを見つめる視点側をだいぶ増やしたせいか。フィロストラトスやディオニスが、従来より立っていたんじゃないかと思う。まあ自分感触なだけだけど。それはそれで新鮮でもあるし、けっして封印する必要はないと思えた。降ってくるばかりが成功じゃない。
しかしね、翌日の釧路では、札幌ではなんとか立ち上がれた清水を呑んだ後のシーンで、股関節不調もあって右足に力が入りきらず、そっち側に倒れこみそうになって石膏胸像を椅子から転げ落として、少し破損させてしまったのだ(あーーー、オーナー、改めてごめんなさーーーい!)。
股関節の衰退もさることながら、前日のダメージがまだ自覚にない状態だったせいでだまされたかもしれない。さらに翌々日の18日くらいにはピークがきたらしく、体のあちこち筋肉痛というか、じわじわだるい状態が自覚できたんですけどね。歳取るってすごいね。疲れがわからない(笑)。
 で、あのシーン、清水を呑んだらメロスはすぐ歩けるようになる進行なので、すっくとすぐに立つようにしてたわけだけど、けど、まっつの今回の体のありようが本当なのかもしれない。
で、あのシーン、清水を呑んだらメロスはすぐ歩けるようになる進行なので、すっくとすぐに立つようにしてたわけだけど、けど、まっつの今回の体のありようが本当なのかもしれない。
つまりそんなにすぐには立ち上がれない。しゃがんだ状態にまで戻って清水をすくって呑めても、そのあと立ち上がるためには、疲労した下肢の状態回復を待たなければならないわけだから、「歩ける」自覚に至るまで、もっと時間かけてもいい。というかかけないとまっつの体がついていけないってことだなあ。
いやメロスだって実はそうだったんじゃないか。だから「歩ける」まで「疲労回復」まで、もっともっと時間かけていいのだ。次にやるときはその線でいこう。若い頃には考えもしなかった、そんな発見がこの体になって出てくるなんて(笑)。
そんなわけで「メロス降りてくるか」みたいな前振りしてたけど(あら?どこに書いたんだっけ。わかんなくなってる(爆)…と思ったら、Xでつぶやいていたのだった…)、結局、上記したように、それとは違う方向の作品になったってことだね。
その中でセリヌンティウスは、フィロストラトスやディオニスのようにフォーカス当てられるターンをまだ見つけられてなかったから、次にはそこらも追求しましょう。
なんていうふうに、まだまだ追求できる方向が見えたので、はい、改めて書いておこう。封印はやめました。そしてアゴアシ付くならどこにでもまいります。投げ銭スタイルでOK。まあ現実には道内限定だろうけど。
来年の2月3月ならけっこう余裕ですぜ。って、ここで書くことじゃ本来ないっぽいけど、まあ企画の後日談な感じでご容赦くださいませませ。
両日とも、メロス以外のこともやったのだけど、それはね、冒険報告をお待ちください。改めて皆様、ありがとうございました。m(_ _)m
作品雑感「走れメロス」(1)・(7)当日用資料 続きを読む
「走れメロス」(8)終了後雑感
[上演を終えて]
メロス2days、思った以上にしっかり手応えあって終えています。まあ案の定、体力の衰えは隠しきれずでしたけど、リハで指摘いただいたように、それがむしろメロスの体のというより、気持ちの強さにつながってくれたみたい。
さすがに釧路での立ちきれずの転倒はよろしくなかったけど(後述)、そういう状態になることを見越した動きは開発できると思う。
//
まずは札幌。いい具合に広さ使えて、方向とか主客スタンスに大きなミスなく手応えあったわ。
そしてどうやら事前に想定していた「メロス降りてくる」タイプの作品では、今回はなくなってたのが分かった。メロスを見つめる視点側をだいぶ増やしたせいか。フィロストラトスやディオニスが、従来より立っていたんじゃないかと思う。まあ自分感触なだけだけど。それはそれで新鮮でもあるし、けっして封印する必要はないと思えた。降ってくるばかりが成功じゃない。
しかしね、翌日の釧路では、札幌ではなんとか立ち上がれた清水を呑んだ後のシーンで、股関節不調もあって右足に力が入りきらず、そっち側に倒れこみそうになって石膏胸像を椅子から転げ落として、少し破損させてしまったのだ(あーーー、オーナー、改めてごめんなさーーーい!)。
股関節の衰退もさることながら、前日のダメージがまだ自覚にない状態だったせいでだまされたかもしれない。さらに翌々日の18日くらいにはピークがきたらしく、体のあちこち筋肉痛というか、じわじわだるい状態が自覚できたんですけどね。歳取るってすごいね。疲れがわからない(笑)。
 で、あのシーン、清水を呑んだらメロスはすぐ歩けるようになる進行なので、すっくとすぐに立つようにしてたわけだけど、けど、まっつの今回の体のありようが本当なのかもしれない。
で、あのシーン、清水を呑んだらメロスはすぐ歩けるようになる進行なので、すっくとすぐに立つようにしてたわけだけど、けど、まっつの今回の体のありようが本当なのかもしれない。つまりそんなにすぐには立ち上がれない。しゃがんだ状態にまで戻って清水をすくって呑めても、そのあと立ち上がるためには、疲労した下肢の状態回復を待たなければならないわけだから、「歩ける」自覚に至るまで、もっと時間かけてもいい。というかかけないとまっつの体がついていけないってことだなあ。
いやメロスだって実はそうだったんじゃないか。だから「歩ける」まで「疲労回復」まで、もっともっと時間かけていいのだ。次にやるときはその線でいこう。若い頃には考えもしなかった、そんな発見がこの体になって出てくるなんて(笑)。
そんなわけで「メロス降りてくるか」みたいな前振りしてたけど(あら?どこに書いたんだっけ。わかんなくなってる(爆)…と思ったら、Xでつぶやいていたのだった…)、結局、上記したように、それとは違う方向の作品になったってことだね。
その中でセリヌンティウスは、フィロストラトスやディオニスのようにフォーカス当てられるターンをまだ見つけられてなかったから、次にはそこらも追求しましょう。
なんていうふうに、まだまだ追求できる方向が見えたので、はい、改めて書いておこう。封印はやめました。そしてアゴアシ付くならどこにでもまいります。投げ銭スタイルでOK。まあ現実には道内限定だろうけど。
来年の2月3月ならけっこう余裕ですぜ。って、ここで書くことじゃ本来ないっぽいけど、まあ企画の後日談な感じでご容赦くださいませませ。
両日とも、メロス以外のこともやったのだけど、それはね、冒険報告をお待ちください。改めて皆様、ありがとうございました。m(_ _)m
作品雑感「走れメロス」(1)・(7)当日用資料 続きを読む
2024年09月13日
「走れメロス」(6)[5の後おまけ]
(1)⇦(5)⇦ 「走れメロス」(6)[5の後おまけ] ⇨(7)当日用資料⇨(8)終了後雑感
蛇足ではありますが…。
 あれこれ方針整理して、先日(24/9/12木)、ひとりでやっててもビシッとこないので、かつて長らくプロデュースをお手伝いくれた旧Pの前でリハーサルしてみました。
あれこれ方針整理して、先日(24/9/12木)、ひとりでやっててもビシッとこないので、かつて長らくプロデュースをお手伝いくれた旧Pの前でリハーサルしてみました。
そしたらですね…叱られました(爆)。
何をって、当日のブログ報告の「かつてやってたありようと比べると、だいぶおとなしい?のか省エネ模様」って書きように、旧Pはかなりご立腹。
曰く『「省エネ」とかではなく、まっつ「メロス」が違う次元に向かったという気がします』ということだそうで、『「おとなしい」「省エネ」の言葉に強く憤ってしま』ったとのこと。
おっとーこれは……むしろ賞賛ではないですかっ!?
指摘してくれたのが『(リハーサルを観てから)ひと晩経って、見えてきた感覚は、「おとなしい」ではなく、「鋭さ」です』。
そして『「心身共にズタボロになって諦めたのが湧き水で復活」するのが、魔法のように復活(心身共にくるりと反転)したのではなく、ズタボロさやいろんな苦さをちゃんと抱えたまま、友の元に走ってゆく姿が胸に刺さったのです』とのこと。
なるほど。って自分で感心することではないけど、悪くない方向に変化したみたい。いやいや、なかなか事前の予想通りにはならないもんだわ。今回はよい方にでよかったあああ!
それは「朗読ではなく読み語りだ」と、胸を張って言えるものになったってことだとも思うので、ちょいとそのへん興味ある人には、ぜひとも目撃していただきたいもんです。そんな奴は、もういないのか(涙;
あー残念ですね、この機会を逃したら、観る機会はきっともうないよ。
(1)・(5) (8)終了後雑感
蛇足ではありますが…。
 あれこれ方針整理して、先日(24/9/12木)、ひとりでやっててもビシッとこないので、かつて長らくプロデュースをお手伝いくれた旧Pの前でリハーサルしてみました。
あれこれ方針整理して、先日(24/9/12木)、ひとりでやっててもビシッとこないので、かつて長らくプロデュースをお手伝いくれた旧Pの前でリハーサルしてみました。そしたらですね…叱られました(爆)。
何をって、当日のブログ報告の「かつてやってたありようと比べると、だいぶおとなしい?のか省エネ模様」って書きように、旧Pはかなりご立腹。
曰く『「省エネ」とかではなく、まっつ「メロス」が違う次元に向かったという気がします』ということだそうで、『「おとなしい」「省エネ」の言葉に強く憤ってしま』ったとのこと。
おっとーこれは……むしろ賞賛ではないですかっ!?
指摘してくれたのが『(リハーサルを観てから)ひと晩経って、見えてきた感覚は、「おとなしい」ではなく、「鋭さ」です』。
そして『「心身共にズタボロになって諦めたのが湧き水で復活」するのが、魔法のように復活(心身共にくるりと反転)したのではなく、ズタボロさやいろんな苦さをちゃんと抱えたまま、友の元に走ってゆく姿が胸に刺さったのです』とのこと。
なるほど。って自分で感心することではないけど、悪くない方向に変化したみたい。いやいや、なかなか事前の予想通りにはならないもんだわ。今回はよい方にでよかったあああ!
それは「朗読ではなく読み語りだ」と、胸を張って言えるものになったってことだとも思うので、ちょいとそのへん興味ある人には、ぜひとも目撃していただきたいもんです。そんな奴は、もういないのか(涙;
あー残念ですね、この機会を逃したら、観る機会はきっともうないよ。
(1)・(5) (8)終了後雑感
2024年08月31日
「走れメロス」(5)
(1)⇦ (4)⇦「走れメロス」(5) ⇨(5の後おまけ) ⇨(7)当日用資料
まっつの読みはどうなる?
今回、シルレルとの比較を通して、太宰の狙いを読み取るようなことになった。最初っからそれを狙ってたわけではないのだけど。
 そこに浮かび上がってきたのは「家族や隣人との平穏な日々」の尊さ。そんなとこだって気がするな。
そこに浮かび上がってきたのは「家族や隣人との平穏な日々」の尊さ。そんなとこだって気がするな。
なにせシルレルでは、フイロストラトスは「メロスの家の留守をしていた忠僕」。つまりメロスはシラクスに住んでいた。それを太宰は「村の牧人」という設定に変えているんだから。
わざわざその点を変更してまで膨らませているのだから、太宰が語り届けたかったことはそのへんのことなんじゃないかな。
別にだからって、それに従わなくちゃいけないとは思わないけど、まあ今回読む際には、せっかくだからその線を強めに残すようにしてみようと、なんとなく思ってる。
ちゃんとそのようになるのかどうかは、まだ未知数だけどね。もう少しあれこれ試してみないと。
一応、今回、従来よりメロスでいる率を下げようと思ってたんだけど、うーん、村との距離感が変わっていくあたりは、やっぱメロス視点に戻しといたほうがいいのかも、なんて思ったり、わあ、なんか悩ましいことになったぞ。
果たして、どうなるか。乞うご期待。(連載・完)
(4)⇦ ⇨(5の後おまけ) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
まっつの読みはどうなる?
今回、シルレルとの比較を通して、太宰の狙いを読み取るようなことになった。最初っからそれを狙ってたわけではないのだけど。
 そこに浮かび上がってきたのは「家族や隣人との平穏な日々」の尊さ。そんなとこだって気がするな。
そこに浮かび上がってきたのは「家族や隣人との平穏な日々」の尊さ。そんなとこだって気がするな。なにせシルレルでは、フイロストラトスは「メロスの家の留守をしていた忠僕」。つまりメロスはシラクスに住んでいた。それを太宰は「村の牧人」という設定に変えているんだから。
わざわざその点を変更してまで膨らませているのだから、太宰が語り届けたかったことはそのへんのことなんじゃないかな。
別にだからって、それに従わなくちゃいけないとは思わないけど、まあ今回読む際には、せっかくだからその線を強めに残すようにしてみようと、なんとなく思ってる。
ちゃんとそのようになるのかどうかは、まだ未知数だけどね。もう少しあれこれ試してみないと。
一応、今回、従来よりメロスでいる率を下げようと思ってたんだけど、うーん、村との距離感が変わっていくあたりは、やっぱメロス視点に戻しといたほうがいいのかも、なんて思ったり、わあ、なんか悩ましいことになったぞ。
果たして、どうなるか。乞うご期待。(連載・完)
(4)⇦ ⇨(5の後おまけ) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
2024年08月24日
「走れメロス」(4)
(3)⇦ 「走れメロス」(4) ⇨(5) ⇨(7)当日用資料
作品ツッコミの続き。
一方、結婚式も含めた自宅シーンは、シルレルではたった2行。王の元から去った次の行ではもう「そして三日目の朝〜急いで急いで妹を夫といっしょにした彼は」帰路についてしまう。
シルレルではタイトル自体が「人質」ってなってるように友人との関係に照準をあててたけど、太宰は家族との関係のことも描いているってことになるかな。でもだったらシルレルさん、友人を名無しですませないでよ。
太宰は、しっかり「ほんとは家にいたい」という内心を何度も出してるほどだもんね。妹に、そして妹婿に、それぞれに対して心境からくる言葉を遺言のように投げかけるほどに。
 そっから先、氾濫する川を渡るシーン、強盗を返り討ちにするシーン、そして動けなくなって清水に救われるシーン。その手順はメロスもシルレルのまま。ただ一点違いがあるとすれば、諦めの心情はシルレルにはない。
そっから先、氾濫する川を渡るシーン、強盗を返り討ちにするシーン、そして動けなくなって清水に救われるシーン。その手順はメロスもシルレルのまま。ただ一点違いがあるとすれば、諦めの心情はシルレルにはない。
この後、状況をそれとなく伝える二人の人の会話内容、フイロストラトスの声かけ、そのへんも基本的な線はそのまま。とはいえ「なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っている」という理由づけは、太宰オリジナルなんだね。(フィロストラトスの立場も変えている)
結末部分でも、ドラマチックな頬を互いに殴らせるシーン、さらに少女がマントを捧げるエピソード、そのどちらも太宰オリジナル。むしろ王が「仲間」になることを望む展開はシルレルにもあったわ。
んー、なんか展開の違いを示すだけで今回は終わってしまって、ちっともツッコミになってない。王の改心あたりが太宰オリジナルだったらツッコんでたとこなのに、原作通りだった。
全体に友人との関係に対して、家族の意義をより強めに持たせたというのが、太宰版の特徴と言えますかね。
(3)⇦ ⇨(5) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
作品ツッコミの続き。
一方、結婚式も含めた自宅シーンは、シルレルではたった2行。王の元から去った次の行ではもう「そして三日目の朝〜急いで急いで妹を夫といっしょにした彼は」帰路についてしまう。
シルレルではタイトル自体が「人質」ってなってるように友人との関係に照準をあててたけど、太宰は家族との関係のことも描いているってことになるかな。でもだったらシルレルさん、友人を名無しですませないでよ。
太宰は、しっかり「ほんとは家にいたい」という内心を何度も出してるほどだもんね。妹に、そして妹婿に、それぞれに対して心境からくる言葉を遺言のように投げかけるほどに。
 そっから先、氾濫する川を渡るシーン、強盗を返り討ちにするシーン、そして動けなくなって清水に救われるシーン。その手順はメロスもシルレルのまま。ただ一点違いがあるとすれば、諦めの心情はシルレルにはない。
そっから先、氾濫する川を渡るシーン、強盗を返り討ちにするシーン、そして動けなくなって清水に救われるシーン。その手順はメロスもシルレルのまま。ただ一点違いがあるとすれば、諦めの心情はシルレルにはない。この後、状況をそれとなく伝える二人の人の会話内容、フイロストラトスの声かけ、そのへんも基本的な線はそのまま。とはいえ「なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っている」という理由づけは、太宰オリジナルなんだね。(フィロストラトスの立場も変えている)
結末部分でも、ドラマチックな頬を互いに殴らせるシーン、さらに少女がマントを捧げるエピソード、そのどちらも太宰オリジナル。むしろ王が「仲間」になることを望む展開はシルレルにもあったわ。
んー、なんか展開の違いを示すだけで今回は終わってしまって、ちっともツッコミになってない。王の改心あたりが太宰オリジナルだったらツッコんでたとこなのに、原作通りだった。
全体に友人との関係に対して、家族の意義をより強めに持たせたというのが、太宰版の特徴と言えますかね。
(3)⇦ ⇨(5) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
2024年08月20日
「走れメロス」(3)
(2)⇦ 「走れメロス」(3) ⇨(4) ⇨(7)当日用資料
今回は作品ツッコミ。

「メロスは激怒した」で始まるこの作品。うまいよね。その後、怒りの発端事情にいったん退いて、そこからその瞬間に向かうシーンを展開する。
初期のソロ読みでは、下手したらこの最初からもうメロス激怒しちゃってたかもだなあ。主体と客体の使い分けがまだまだ甘かったというべきか。
あららそれだと、作品ツッコミではなく、まっつツッコミではないか。…そんなことじゃなくて。
最初に「?」ってなるのは、多くの人がそうかどうかわからんけど、今回改めてテスト読みしたときにも思ったのだが、セリヌンティウスを身代わりにする展開部分。あまりに簡単ですぎないか。他にもそういう指摘は多々あるようですけど。
久々に会いにきて、でもまだ会えてないんだよ。身代わりにするとしてももう少し申し出方というか、当人への伝え方に対して配慮あっていいんじゃないか。そんな違和感。
さて本文最後に記された出典「シルレルの詩」のシルレルって、シラーのことなんだってね。あんまり海外詩を知らない人でも、シラーという名は聞いたことあるかもだよね。ベートーベン「第九」歓喜の歌の原詩もこの人。
お伝えしたいのは、そのシルレルの詩と比較してのこと。太宰のこの作品は、シルレル作品「人質」に対して、削ったシーンより新たに加えたシーンのほうが圧倒的に多いのだけど、このシーン、シルエルでは友をメロスが尋ねて事情を説明し「人質」になってもらう展開だったのが、太宰ではそれがなくて、刑場に連れてこられた友と久々に「相逢う」のだ。
なんだろな、これ。この割愛。自分から説明にいって身代わりになってもらうのと、もう連れてこられて身代わりにならざるを得なくなった相手に事情を説明するのとでは、相手との関係、だいぶ違わないか。太宰のメロスはセリヌンティウスに対して、「無慈悲」にすら思えてくる。いくら「単純な男」とはいえ。「竹馬の友」といえ。
太宰は、どうしてそうしたんだろう。勝手な推論だが、太宰はそのくらいにお互い信頼できる関係を、激しく希求してたってことなんじゃないか。そしてそれはその気持ちの底に、ここに登場する王「ディオニス」と同じように「信頼への疑念」があったからこそなのかもしれない。(強引)
ついでにいうと、シラーはこの「友」の名は記してない。フィロストラトスの名はしっかり登場させているのに。
(2)⇦ ⇨(4) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
今回は作品ツッコミ。

「メロスは激怒した」で始まるこの作品。うまいよね。その後、怒りの発端事情にいったん退いて、そこからその瞬間に向かうシーンを展開する。
初期のソロ読みでは、下手したらこの最初からもうメロス激怒しちゃってたかもだなあ。主体と客体の使い分けがまだまだ甘かったというべきか。
あららそれだと、作品ツッコミではなく、まっつツッコミではないか。…そんなことじゃなくて。
最初に「?」ってなるのは、多くの人がそうかどうかわからんけど、今回改めてテスト読みしたときにも思ったのだが、セリヌンティウスを身代わりにする展開部分。あまりに簡単ですぎないか。他にもそういう指摘は多々あるようですけど。
久々に会いにきて、でもまだ会えてないんだよ。身代わりにするとしてももう少し申し出方というか、当人への伝え方に対して配慮あっていいんじゃないか。そんな違和感。
さて本文最後に記された出典「シルレルの詩」のシルレルって、シラーのことなんだってね。あんまり海外詩を知らない人でも、シラーという名は聞いたことあるかもだよね。ベートーベン「第九」歓喜の歌の原詩もこの人。
お伝えしたいのは、そのシルレルの詩と比較してのこと。太宰のこの作品は、シルレル作品「人質」に対して、削ったシーンより新たに加えたシーンのほうが圧倒的に多いのだけど、このシーン、シルエルでは友をメロスが尋ねて事情を説明し「人質」になってもらう展開だったのが、太宰ではそれがなくて、刑場に連れてこられた友と久々に「相逢う」のだ。
なんだろな、これ。この割愛。自分から説明にいって身代わりになってもらうのと、もう連れてこられて身代わりにならざるを得なくなった相手に事情を説明するのとでは、相手との関係、だいぶ違わないか。太宰のメロスはセリヌンティウスに対して、「無慈悲」にすら思えてくる。いくら「単純な男」とはいえ。「竹馬の友」といえ。
太宰は、どうしてそうしたんだろう。勝手な推論だが、太宰はそのくらいにお互い信頼できる関係を、激しく希求してたってことなんじゃないか。そしてそれはその気持ちの底に、ここに登場する王「ディオニス」と同じように「信頼への疑念」があったからこそなのかもしれない。(強引)
ついでにいうと、シラーはこの「友」の名は記してない。フィロストラトスの名はしっかり登場させているのに。
(2)⇦ ⇨(4) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
2024年08月18日
「走れメロス」(2)
(1)⇦ 「走れメロス」(2) ⇨(3) ⇨(7)当日用資料
 2007年初演のときから「走れメロス」でまっつは走ってたみたいなんだ。といっても狭いスペースでのライブがほとんどだったから、ほぼ全面的にスタンディングラン。ただその最盛期にもっとも広くスペースを使えた2009年やまびこ座での上演時には、スタンディングランが軸ではあるけど、行き来描写の強いとこではけっこう広く走り回ったりもしていたわ。
2007年初演のときから「走れメロス」でまっつは走ってたみたいなんだ。といっても狭いスペースでのライブがほとんどだったから、ほぼ全面的にスタンディングラン。ただその最盛期にもっとも広くスペースを使えた2009年やまびこ座での上演時には、スタンディングランが軸ではあるけど、行き来描写の強いとこではけっこう広く走り回ったりもしていたわ。
冒険報告「やまびこ座」メロス上演まっつBOOKing first-4
あ、これ、一部はYouTubeで映像公開していました。
冒頭部分(劇場版「走れメロス」1)。ここは走るシーンじゃないけどね。
改めて見たら、なんかずいぶん口が回ってるなあ。今はここまでの速度では読まないだろうなあ。でも、あらあら、なかなかおもしろいじゃないの。そしてちなみに当時は、メロス以外の人物のセリフのとき以外は、ほとんどメロス主格のスタンスで動いてた。きっと今ならそうしない。体力的な問題が大きいけど、それだけでなくたぶんもっと「間」を多用すると思う。
 YouTubeには、5分割したうちのもうひとつ載せてる。最後の前。
YouTubeには、5分割したうちのもうひとつ載せてる。最後の前。
磔台に上るまで(劇場版「走れメロス」4/5)
ここがほとんど走りのシーン、中でもいろんな場を巡るシーンではステージ内走り回ってた。
そして驚いたことに、この2009年劇場版では、広いスペースを使ったにもかかわらず、32分半で読み終えてました。初期ソロで37分くらいだったものが、かえって展開速くなってたんだな。
これ、メロスも急いでたけど、まっつも急いじゃっていたのかもですね。
(追記)ちなみに今回取り上げる以前、最後にメロスをやったのは、2013年7月)。唯一の音楽とのコラボスタイルのときだったみたい。わお、そこからでももう10年も経ってる。たとえ望んだとしても、同じようにはできませんね(爆)。
(1)⇦ ⇨(3) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
 2007年初演のときから「走れメロス」でまっつは走ってたみたいなんだ。といっても狭いスペースでのライブがほとんどだったから、ほぼ全面的にスタンディングラン。ただその最盛期にもっとも広くスペースを使えた2009年やまびこ座での上演時には、スタンディングランが軸ではあるけど、行き来描写の強いとこではけっこう広く走り回ったりもしていたわ。
2007年初演のときから「走れメロス」でまっつは走ってたみたいなんだ。といっても狭いスペースでのライブがほとんどだったから、ほぼ全面的にスタンディングラン。ただその最盛期にもっとも広くスペースを使えた2009年やまびこ座での上演時には、スタンディングランが軸ではあるけど、行き来描写の強いとこではけっこう広く走り回ったりもしていたわ。冒険報告「やまびこ座」メロス上演まっつBOOKing first-4
あ、これ、一部はYouTubeで映像公開していました。
冒頭部分(劇場版「走れメロス」1)。ここは走るシーンじゃないけどね。
改めて見たら、なんかずいぶん口が回ってるなあ。今はここまでの速度では読まないだろうなあ。でも、あらあら、なかなかおもしろいじゃないの。そしてちなみに当時は、メロス以外の人物のセリフのとき以外は、ほとんどメロス主格のスタンスで動いてた。きっと今ならそうしない。体力的な問題が大きいけど、それだけでなくたぶんもっと「間」を多用すると思う。
 YouTubeには、5分割したうちのもうひとつ載せてる。最後の前。
YouTubeには、5分割したうちのもうひとつ載せてる。最後の前。磔台に上るまで(劇場版「走れメロス」4/5)
ここがほとんど走りのシーン、中でもいろんな場を巡るシーンではステージ内走り回ってた。
そして驚いたことに、この2009年劇場版では、広いスペースを使ったにもかかわらず、32分半で読み終えてました。初期ソロで37分くらいだったものが、かえって展開速くなってたんだな。
これ、メロスも急いでたけど、まっつも急いじゃっていたのかもですね。
(追記)ちなみに今回取り上げる以前、最後にメロスをやったのは、2013年7月)。唯一の音楽とのコラボスタイルのときだったみたい。わお、そこからでももう10年も経ってる。たとえ望んだとしても、同じようにはできませんね(爆)。
(1)⇦ ⇨(3) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
2024年08月17日
「走れメロス」(1)
「走れメロス」(1) ⇨(2) ⇨(7)当日用資料
 初めてメロスを知ったのは、たぶん国語の教科書。おそらく中学時代かと思う。今でも中学校教科書に載ってるらしいよね。自分が読んだのは全文だったのかなあ。きっと違うな。と思ったら「のちに問題と なる『少女の場面』も省略されておらず、全文が採録されている。(《1956 年、教材「走れメロス」の生成》より)」。自分も全文読んでたってことか。
初めてメロスを知ったのは、たぶん国語の教科書。おそらく中学時代かと思う。今でも中学校教科書に載ってるらしいよね。自分が読んだのは全文だったのかなあ。きっと違うな。と思ったら「のちに問題と なる『少女の場面』も省略されておらず、全文が採録されている。(《1956 年、教材「走れメロス」の生成》より)」。自分も全文読んでたってことか。
まあそれによって、そこそここのお話は記憶残ったはずとは思う。ただし学校でこの作品を通して何を習ったかは覚えてない。なにせ50年以上前の話だしね(^^;
次にはっきり意識して読んだのは、中学生当時からは35年以上経った2007年。はい、読み語りました。
参照:冒険報告「2007.5.26紅茶夜会12」
この報告文中からリンクしている「ニュアージュさんブログ」はまだ残存してて、そこでは当時のまっつの姿も見られる(爆)。わ、今からだと17年前なのかあああ。
(続…いた) ⇨(2) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
 初めてメロスを知ったのは、たぶん国語の教科書。おそらく中学時代かと思う。今でも中学校教科書に載ってるらしいよね。自分が読んだのは全文だったのかなあ。きっと違うな。と思ったら「のちに問題と なる『少女の場面』も省略されておらず、全文が採録されている。(《1956 年、教材「走れメロス」の生成》より)」。自分も全文読んでたってことか。
初めてメロスを知ったのは、たぶん国語の教科書。おそらく中学時代かと思う。今でも中学校教科書に載ってるらしいよね。自分が読んだのは全文だったのかなあ。きっと違うな。と思ったら「のちに問題と なる『少女の場面』も省略されておらず、全文が採録されている。(《1956 年、教材「走れメロス」の生成》より)」。自分も全文読んでたってことか。まあそれによって、そこそここのお話は記憶残ったはずとは思う。ただし学校でこの作品を通して何を習ったかは覚えてない。なにせ50年以上前の話だしね(^^;
次にはっきり意識して読んだのは、中学生当時からは35年以上経った2007年。はい、読み語りました。
参照:冒険報告「2007.5.26紅茶夜会12」
この報告文中からリンクしている「ニュアージュさんブログ」はまだ残存してて、そこでは当時のまっつの姿も見られる(爆)。わ、今からだと17年前なのかあああ。
(続…いた) ⇨(2) ⇨(7)当日用資料 続きを読む
2024年06月14日
「谷川俊太郎のQとA」プラス・内容関連(1)
[関連]告知・連載(3)・連載(2)
 前半の眼目として今回読み語っていくのは、俊カフェ蔵書の谷川さん著作からではあるのですが、詩集でもなく絵本でもなく、こんな著作からのQやAです。
前半の眼目として今回読み語っていくのは、俊カフェ蔵書の谷川さん著作からではあるのですが、詩集でもなく絵本でもなく、こんな著作からのQやAです。
『谷川俊太郎質問箱』
『星空の谷川俊太郎質問箱』
『谷川俊太郎の33の質問』
『谷川俊太郎の33の質問 続』
考えてみたら、こういうタイプの文章を読み語りしたことって、一瞬リクエストではあったかもしれないけど、これだけたっぷりやるのは初めてかも。
どう攻略(笑)していくか、けっこう考えました。そんなとこらへんもここでお知らせしていけたらとは思っていまっつ。どうかお楽しみに。
[関連]告知・連載(3)・連載(2) 続きを読む
 前半の眼目として今回読み語っていくのは、俊カフェ蔵書の谷川さん著作からではあるのですが、詩集でもなく絵本でもなく、こんな著作からのQやAです。
前半の眼目として今回読み語っていくのは、俊カフェ蔵書の谷川さん著作からではあるのですが、詩集でもなく絵本でもなく、こんな著作からのQやAです。『谷川俊太郎質問箱』
『星空の谷川俊太郎質問箱』
『谷川俊太郎の33の質問』
『谷川俊太郎の33の質問 続』
考えてみたら、こういうタイプの文章を読み語りしたことって、一瞬リクエストではあったかもしれないけど、これだけたっぷりやるのは初めてかも。
どう攻略(笑)していくか、けっこう考えました。そんなとこらへんもここでお知らせしていけたらとは思っていまっつ。どうかお楽しみに。
[関連]告知・連載(3)・連載(2) 続きを読む
2019年04月23日
「注文の多い料理店・序」
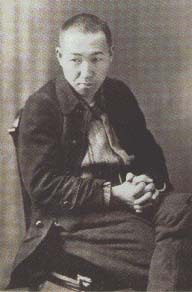 童話集「注文の多い料理店」の巻頭を飾る賢治の自序。掲載した「おはなし」を発表するにあたって、作者・賢治の姿勢が綴られている。
童話集「注文の多い料理店」の巻頭を飾る賢治の自序。掲載した「おはなし」を発表するにあたって、作者・賢治の姿勢が綴られている。まっつは、自分が読み語りをするときの姿勢に通じるところを感じてしまっていて、初期の頃、かなり好んで読んできたんだよね。半ば自己紹介代りにさえしていたくらいに。
どう「通じるところ」を感じてるかっていうと、つまりねー「なんのことやらわけのわからない」ところがあっても「ほんとうのたべものに」なるように読みたいってこと。うーん、そのまんまじゃないんだけど、どう説明したらいいだろう。
賢治がこの童話集の後、生前に発表した作品はごくわずか。今日知られる「代表作」のほとんどが死後、半ば発掘されるように刊行されたもの。そして彼は、それらを何度も改稿している。「永久の未完成これ完成である」との言葉が示唆するように。もしかするとそれは、「注文の多い料理店」が意に沿わず売れなかったせいという面もあるかもしれない。
でも、そんなあとの状態があるにしても、この童話集を出したときは、この序にあるように「そのとおり書いたまで」だったはずで、きっと微笑ましく送り出したんじゃないかと思うのさ。後の賢治の姿勢よりも、まっつはこの時の賢治の姿勢に組したい。
「そのとおり書いたまで」と同じように、まっつは「そのとおり読んでいるまで」というつもり。わからなくても、読んでここにある言葉の何かを伝えることはできる、と、まっつは信じていて、それがなんか彼のこの言葉とつながっていると思ってるわけですわ。とりわけ「その場リクエスト」を読むときなんて、ホントにわからないまま読み出して、読み進めながら理解していくことも多いわけだし。
ところで最近は、自己紹介的に使うことは減ってきていて、むしろこれを「読んでもらう」ことのほうが多くなっている。そして、どんな読み方をされても色あせないこの文章、やっぱり大好きなんだなあ。と思ってまっつ。
なお、札幌人図鑑 第586回の動画3 6:32あたりから3分ほどでお聴きいただけます。福津さんに改めて感謝。聴き手が見えない状況のせいだろうな、なんかちょっと必要以上にゆっくりになってる気がするけど(笑)。
[読み語り所要時間]2分-3分 続きを読む
2019年04月13日
「どんぐりと山猫」
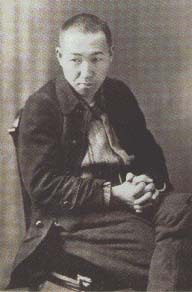 童話集「注文の多い料理店」の冒頭を飾る作品です。何度かは読み語っているけど、しばらくやってなかったので、改めて工夫どころを検討するような雑感です。
童話集「注文の多い料理店」の冒頭を飾る作品です。何度かは読み語っているけど、しばらくやってなかったので、改めて工夫どころを検討するような雑感です。地の文は、終始、主格のこども側に立ってますね、一人称じゃないけど。こどもが見聞きして捉えたことだけを代弁している感じ。しかもそれでほぼ、問題ない。まあ、こどもが意識してなかった事に扱うことができなくもない叙述も少しはある。でもあえてそうする理由は積極的にはないし、そこに挑戦する段階ではないので、そこはあんまり考えない。
楽しいのはやっぱりどんぐりたちの言い分。その繰り返しが文面としてだんだん省略されていくとこあたり。彼らの懸命さと、それに対するやまねこのいらだちや諦観、そして対照的なこどもの冷静さは、一人称で書いてたら示し切れなかったとこかもしれない。なんて思うと、やっぱ王道的にその盛り上がりをどう作るかがポイントなんだよなあ。
そしてもうひとつ、そのメインシーンでは脇役に徹している馬車別当。脇役なのに一番造形されている奴。こいつの印象をどう残すかっていうのも楽しみどころだよね。
[読み語り(ソロ)所要時間]17分-20分 続きを読む
2019年04月08日
「注文の多い料理店」
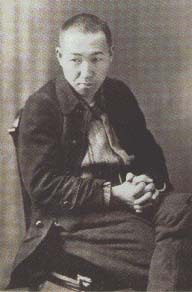 宮沢賢治が生前に唯一刊行した童話集であり、かつそこに収録された表題作ですね。作品の解釈とかテーマとか、そういう点はあまりふれず、基本的に読み語りをする上で感じていることなどを書こうと思います。
宮沢賢治が生前に唯一刊行した童話集であり、かつそこに収録された表題作ですね。作品の解釈とかテーマとか、そういう点はあまりふれず、基本的に読み語りをする上で感じていることなどを書こうと思います。まっつの20年近い読み語り歴の中、この童話はもっとも回数多く取り組んできた小説系作品のひとつです。これに匹敵する小説系は、芥川の「蜘蛛の糸」くらいかなあ。あ、楠山「ねずみのよめいり」もかなりか。
まあその羅列はどうでもいいんですが、そのように回を重ねているので、当然、読み方も多少変遷してきてます。年を経て確認しようと思ったら、わ、初期というか2011年まであたり音声データは…いまはもう聞けないじゃないかっ。ああー、MD…。
そんなわけで、きっちり振り返るのは難しいので、今、この作品についてどう感じ、どう意識しながら読むかということを披露しつつ、多少その中でかつての読みのことが思い浮かんだら示していくにとどめます。
まずは主要登場人物である「二人の紳士」。ともに「肥って若い」ってことなので、差異を出すのに最近はだいたい、ひとりはおおざっぱ。もうひとりは少し下手に出て優位に立ちたがる。そんなイメージにしていますね。ステイタス的には前者のほうがちょっとだけ上の感じ。
これがはまるのは、戸に書かれた指示に少しは疑念を持ちながらも、後者が思いつきでもっともらしいことを言って問題ないことにしてしまう、という流れがおおむねあるから。たぶん初期のころは、そこまで明確に意識してなかったと思うけど、だんだん、そうやって二人が追い詰められていく中に、両者の必ずしも健全ではない関係性があるのがおもしろいと思い始めたんだよね。これ、最近はけっこう鉄板な感じで採用してる。
まあそれでほぼ進行して、もうひとつ大きなポイントは終盤の戸の中から聞こえる声ですね。これ初期は体ごと切り替えて戸の向こうの存在(明示されてないけど山猫の子分たち)になってやってたと思うんだけど、いつのころからか、体は紳士たちのままで、声だけそいつらにする、というやり方にしてるんですね。
どういうことやらわかりませんね。そこはライヴでお楽しみくださいませ。(19.04.08)
[読み語り(ソロ)所要時間]15分-17分半(19.04.13追記) 続きを読む
2014年11月23日
「夢十夜」について
「夢十夜」
1908年(明治41年)の夏に新聞連載。漱石には珍しい短編連作。その幽玄多彩な作品世界は、映画などにもなっている。
「夏目漱石」
「坊ちゃん」「吾輩は猫である」等の長編小説で著名な小説家。1867年2月9日(慶応3年1月5日)生誕、1916年(大正5年)12月9日没。2004年発行分まで千円札に肖像が使われたことで覚えている人も多いかもしれない。
[まっつ的「夢十夜」紹介]
ご存知、夏目漱石の手による短編連作。いや、漱石作品を読んだことのある人でも、この短編群は知らないって人も多いっすね。
ざっと見渡してみても、漱石の作品は読み語りには向かないものが多いんです。・・長いから。いや、一部抜粋という形であればいいんだろうけど、なかなかそれってむずかしいですよ。
「小品」とされる作品はそこそこある。ただそれって小説なんだかエッセイなんだか、しっかり研究してない自分には区別が付かないんですよね。
そんな中でこの「夢十夜」は、さすが「夢」と題しているだけあって、幻想小説って言っちゃっていいだろうと思える次第。
作者の時代を舞台とする篇が多いものの、江戸時代を思わせる篇や、はるか古えを舞台にしたものもある。とはいえ夢にありがちな妖怪変化の類いは、明確な形では登場しない。「どっちなの」というやや曖昧な登場が、むしろ夢らしいといえば夢らしい。
地の文の筆致も、明らかに登場主体人物として語られている篇から、夢にいて観察している側のものであったり、登場人物筆致でありつつはるか彼方を描写する篇もある。さらに最後に伝聞と分かる展開や、伝聞を観ていたような語り口で続けていく篇もある。
そのあたりの多様性も、何度読んでも飽きない要因じゃないかな。
そんな風に、このところはすごく親しげにこの十篇と付き合っているまっつですが、ちゃんと読んだのは、まあなんと、読み語りを初めてから、なのです。読み語りにふさわしい作品を探してのことだったんですね(確か)。
高校時代、漱石長編は読破してやろうと思って、とにかくも読み切ったんですけど、短いものは「倫敦等」の???な感じに入っていけず、以後挫折したって記憶があるくらい。だから読んでなかったはず。ま、長編についても「読んだ記憶」があるだけで、中身はもうほとんど思い出せないくらいだから、どうってことないことですけどね(笑)。
ざくっと内容を知りたいなら、Wikiに各篇紹介が載ってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/夢十夜
そして全篇とも「青空文庫」で読めます。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/799_14972.html
→「夢十夜」について2-各夜 続きを読む
1908年(明治41年)の夏に新聞連載。漱石には珍しい短編連作。その幽玄多彩な作品世界は、映画などにもなっている。
「夏目漱石」

「坊ちゃん」「吾輩は猫である」等の長編小説で著名な小説家。1867年2月9日(慶応3年1月5日)生誕、1916年(大正5年)12月9日没。2004年発行分まで千円札に肖像が使われたことで覚えている人も多いかもしれない。
[まっつ的「夢十夜」紹介]
ご存知、夏目漱石の手による短編連作。いや、漱石作品を読んだことのある人でも、この短編群は知らないって人も多いっすね。
ざっと見渡してみても、漱石の作品は読み語りには向かないものが多いんです。・・長いから。いや、一部抜粋という形であればいいんだろうけど、なかなかそれってむずかしいですよ。
「小品」とされる作品はそこそこある。ただそれって小説なんだかエッセイなんだか、しっかり研究してない自分には区別が付かないんですよね。
そんな中でこの「夢十夜」は、さすが「夢」と題しているだけあって、幻想小説って言っちゃっていいだろうと思える次第。
作者の時代を舞台とする篇が多いものの、江戸時代を思わせる篇や、はるか古えを舞台にしたものもある。とはいえ夢にありがちな妖怪変化の類いは、明確な形では登場しない。「どっちなの」というやや曖昧な登場が、むしろ夢らしいといえば夢らしい。
地の文の筆致も、明らかに登場主体人物として語られている篇から、夢にいて観察している側のものであったり、登場人物筆致でありつつはるか彼方を描写する篇もある。さらに最後に伝聞と分かる展開や、伝聞を観ていたような語り口で続けていく篇もある。
そのあたりの多様性も、何度読んでも飽きない要因じゃないかな。
そんな風に、このところはすごく親しげにこの十篇と付き合っているまっつですが、ちゃんと読んだのは、まあなんと、読み語りを初めてから、なのです。読み語りにふさわしい作品を探してのことだったんですね(確か)。
高校時代、漱石長編は読破してやろうと思って、とにかくも読み切ったんですけど、短いものは「倫敦等」の???な感じに入っていけず、以後挫折したって記憶があるくらい。だから読んでなかったはず。ま、長編についても「読んだ記憶」があるだけで、中身はもうほとんど思い出せないくらいだから、どうってことないことですけどね(笑)。
ざくっと内容を知りたいなら、Wikiに各篇紹介が載ってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/夢十夜
そして全篇とも「青空文庫」で読めます。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/799_14972.html
→「夢十夜」について2-各夜 続きを読む
2014年11月23日
「夢十夜」について2-各夜
読み語り的「夢十夜」各夜解説(爆)
「夢十夜」作品全体については
→「夢十夜」について1
・全十篇のうち「こんな夢を見た」で始まるのが「第一夜」「第二夜」「第三夜」「第五夜」。後は「第九夜」が「夢の中で母から聞いた」で終わります。が、残り半分の5篇には「夢」なんて一言も書いてない。でもまあほとんどが明らかに「夢」として描かれていると読むしかないんじゃないかな。
[第一夜]
・最も有名だろうと思われる篇。「こんな夢を見た」に続いて「女がもう死にますと云う」てな文が来ます。
・終始、地の文は男性視点。でも女セリフが十篇中で最も多い。それも今にも死にそうなはかなげなコトバだからか、女性の選択が第一期では多めでした。
・文字数も十篇中最大。それに加えて時間経過の大きい内容のためか、たいてい全篇で一番時間がかかります。
・舞台は終始、男の(と思われる)家の居室と庭。そこで「百年」。
・最後の一文に、どんな想いを乗せるかで、きっと印象は大きく変わるだろうなあ。
☆読み語り初期の頃は、女セリフは女視線でやってたんだけど、最近はなんか男視線のままで女セリフを言うようになってる。
[第二夜]
・全篇中、おそらく最も緊迫感の高い篇。声を荒げるというより静かに殺気がみなぎっていく感じだけど、それでも一番、汗をかく(笑)。
・「」で括られていない和尚のコトバをどう読むか。そこらには選択の余地がありますね。
・読み語り的には、小道具である「短刀」とか、「行灯」を始めとする部屋のしつらえをどこまで具現化するかが工夫のしどころ。
・最後の一文の後に、どんなイメージを残すかってとこには、まだまだいろんな可能性がありそう。
☆これも初期には実際に座ってやったりもしてたけど、最近そのスタイルはやってないなあ。今期「夢十夜Nights」では、当たったらそのスタイルも久々にやってみようかな。
[第三夜]
・「夢十夜」が「怪談」と紹介されることもそちこちであるようですが、最も怪談らしいのがこの篇。そっち方面(どこ?)では一番有名かも。
・第二夜のような殺気みなぎる緊迫感ではなく、怪しさに浸食されて次第に切迫していく感じ。
・「背負った子供(小僧)と会話する」という状況設定が、とにかく怪談めく効果を与えているよねぇ。
・最後に百年前のことを想い出すと…、という展開は、なんで怖いのか論理的にはうまく説明できないけど、確かに怖い。
・全篇中、最も会話文が多い。
☆これは初期のころと今とで、そんなに読み方は変わってないな。身体の使い方はだいぶ少なくなってきたけど。小僧の声はちょっと安定しすぎか、たまに違う声にしてもみてもいいかなあ。
[第四夜]
・一転して子ども目線で描かれた篇。これも怪談というなら怪談だけど、怖いというよりただただ「不思議」に満たされた感じ。
・妙なじいさんに心惹かれてこっそりついていく子ども。どことなく「ハーメルンの笛吹き男」を思わせるのだが、そして確かに笛を吹くのだが、子どもは最後、じいさんと関わることもなく置いてかれる。
・その最終景をどんな風に印象づけるか、は、いろんなやり方があると思ってる。
☆「じいさん」の造型で、おそらくずいぶん印象が変わるんだろうと思うのだが、まっつはけっこう同じにやってるなあ。でもこれはけっこう鉄板な感覚。
※「神さん」は、当時の表記のあり方からすると「おかみさん」の意で間違いないと思われるのだが、ときどき「神様」の意で読むこともある。
●ちなみに、谷川俊太郎さんの「じゅうにつき」の「くがつ」に出てくる「おじいさん」のモデルはこの「じいさん」じゃないかと勝手に思ってる(笑)。
[第五夜]
・全篇中、もっとも古い時代を舞台にした篇。「神代に近い昔と思われる」とあるんだからそうでしょ。夢の話だからまあ、正確かどうかは問題ではないけど、そんなもんかなと思わせるのはさすが。
・語り手である男と、彼を捕えた大将との対峙シーンから、一転してそのままの語り口で遠くの女を描く。
・その視点の移動も大きいけど、よく読むとそこまでにも当事者としての語りというより解説挿入的な部分がけっこう入っている。
☆そんなわけで当事者目線で読むときも多いけど、ときどき第三者目線でやってみたりする。
[第六夜]
・「鎌倉時代とも思われる」ような場所に運慶がいる。木の高いところにいて「仁王を刻んでいる」らしい。「ところが見ているものは」「明治の人間」。
・そうしてもっぱら見物視線から運慶の様子を描ききるのかと思わせつつ、意外にも途中でその場とはお別れ。「急に自分も仁王が彫ってみたくなった」のだ。
・そんなわけで最後の場面では、「明治の木にはとうてい仁王は埋っていない」と悟る。悟るのは悟るでそれでいいのだが、その締めが「それで運慶が今日まで生きている理由もほぼ解った」。読者としても一瞬「解った」気になるのだが、よくよく考えると理屈は通ってない。
☆読み手としてはしかしだからこそ、どれだけ「解った」気にさせるかだよなと思ったりする。
[第七夜]
・舞台はさらにここまでの作品と毛色の違う場が舞台。船である。「けれどもどこへ行くんだか分らない」。
・終始、地の文は当事者スタンスで展開。そして「つまらないから死のうとさえ思って」いく。
・登場して何かを言う人の数は、全篇で一番多い。
・ただねー「」で括ってるセリフと、そうじゃないセリフとが混在しているのがちょっとひっかかるんだよねえ。
☆ひっかかるけど、まあセリフだろうと言うのは通常セリフ的に読んでいることが多いなあ。
☆これも最後の一文をどう聴かせるか。そこに至るまでに何を積み重ねるかが大きい篇だと思う。「どこへ行くんだか分らない」船に、それまでにどれだけリアリティを積み重ねるか。
[第八夜]
・一転、日常的な場(であったろう)、床屋が舞台。
・全体を通じて「鏡」に映る「窓の外を通る往来」を気にする当事者視線で描かれている。
・最後に「帳場格子」の「女」が見えるのだが、そこから急に「不思議」が立ち上がる。
・そして「金魚売」。
☆最後の一文で、この金魚売をどんな風情で「眺めている」ようにするか。その振り幅は多分、全篇中一番大きい。つまり一番捉えどころがない篇(笑)。
[第九夜]
・これまた一転して、今度は終始、第三者視線で描かれた篇。唯一、女性が主役のお話と言ってもいいだろう。
・ときどき地の文は主役から目を離し、あたりにある物を「面白い」などとも語ってしまう。
・そのくせそれは「夢の中で母から聞いた」話だって最後に締めるんだよね。この最終文とその前の文で二段落ちだよね。
☆クライマックスの「お百度参り」シーンには、主役のセリフは出てこない。まあだから第三者視線の地の文ながら、主役の心境をつい忍ばせたくなる。そうやってることが多いのだけど、もっと見守る側でいてもいいんだろうなあ。
[第十夜]
・全十篇中、唯一、笑いが出ることのある篇。まあ「くすっ」程度だけど。
・そして「第八夜」に登場した固有名詞の人物「庄太郎」が主役という、他の篇にはない特徴がある。
・とはいえ筆致は第三者視点。第三者だけど知り合いスタンスなのも特徴的か。
・ここに出てくる「女」は、しかしかなり怪しい。そしてこの篇ではセリフ的表現にまったく「」がない。
☆この「女」をどう造型するかってのが、読み語り的には一番の工夫どころかも。
●読者としては、第八夜に出てくる庄太郎の「連れ」の「女」と、この篇の「女」を同じと読むのも許されるだろう。しかしまあ、一貫して一人で読み語っても、そこを表現するってのはムリ。
と、こんなふうに全十篇を改めて解説風スタンスで見てきたら、あらあら、第一夜と第十夜、最初と最後の篇が共に、「女に何か要求されるお話」だったんですねえ。 続きを読む
「夢十夜」作品全体については
→「夢十夜」について1
・全十篇のうち「こんな夢を見た」で始まるのが「第一夜」「第二夜」「第三夜」「第五夜」。後は「第九夜」が「夢の中で母から聞いた」で終わります。が、残り半分の5篇には「夢」なんて一言も書いてない。でもまあほとんどが明らかに「夢」として描かれていると読むしかないんじゃないかな。
[第一夜]
・最も有名だろうと思われる篇。「こんな夢を見た」に続いて「女がもう死にますと云う」てな文が来ます。
・終始、地の文は男性視点。でも女セリフが十篇中で最も多い。それも今にも死にそうなはかなげなコトバだからか、女性の選択が第一期では多めでした。
・文字数も十篇中最大。それに加えて時間経過の大きい内容のためか、たいてい全篇で一番時間がかかります。
・舞台は終始、男の(と思われる)家の居室と庭。そこで「百年」。
・最後の一文に、どんな想いを乗せるかで、きっと印象は大きく変わるだろうなあ。
☆読み語り初期の頃は、女セリフは女視線でやってたんだけど、最近はなんか男視線のままで女セリフを言うようになってる。
[第二夜]
・全篇中、おそらく最も緊迫感の高い篇。声を荒げるというより静かに殺気がみなぎっていく感じだけど、それでも一番、汗をかく(笑)。
・「」で括られていない和尚のコトバをどう読むか。そこらには選択の余地がありますね。
・読み語り的には、小道具である「短刀」とか、「行灯」を始めとする部屋のしつらえをどこまで具現化するかが工夫のしどころ。
・最後の一文の後に、どんなイメージを残すかってとこには、まだまだいろんな可能性がありそう。
☆これも初期には実際に座ってやったりもしてたけど、最近そのスタイルはやってないなあ。今期「夢十夜Nights」では、当たったらそのスタイルも久々にやってみようかな。
[第三夜]
・「夢十夜」が「怪談」と紹介されることもそちこちであるようですが、最も怪談らしいのがこの篇。そっち方面(どこ?)では一番有名かも。
・第二夜のような殺気みなぎる緊迫感ではなく、怪しさに浸食されて次第に切迫していく感じ。
・「背負った子供(小僧)と会話する」という状況設定が、とにかく怪談めく効果を与えているよねぇ。
・最後に百年前のことを想い出すと…、という展開は、なんで怖いのか論理的にはうまく説明できないけど、確かに怖い。
・全篇中、最も会話文が多い。
☆これは初期のころと今とで、そんなに読み方は変わってないな。身体の使い方はだいぶ少なくなってきたけど。小僧の声はちょっと安定しすぎか、たまに違う声にしてもみてもいいかなあ。
[第四夜]
・一転して子ども目線で描かれた篇。これも怪談というなら怪談だけど、怖いというよりただただ「不思議」に満たされた感じ。
・妙なじいさんに心惹かれてこっそりついていく子ども。どことなく「ハーメルンの笛吹き男」を思わせるのだが、そして確かに笛を吹くのだが、子どもは最後、じいさんと関わることもなく置いてかれる。
・その最終景をどんな風に印象づけるか、は、いろんなやり方があると思ってる。
☆「じいさん」の造型で、おそらくずいぶん印象が変わるんだろうと思うのだが、まっつはけっこう同じにやってるなあ。でもこれはけっこう鉄板な感覚。
※「神さん」は、当時の表記のあり方からすると「おかみさん」の意で間違いないと思われるのだが、ときどき「神様」の意で読むこともある。
●ちなみに、谷川俊太郎さんの「じゅうにつき」の「くがつ」に出てくる「おじいさん」のモデルはこの「じいさん」じゃないかと勝手に思ってる(笑)。
[第五夜]
・全篇中、もっとも古い時代を舞台にした篇。「神代に近い昔と思われる」とあるんだからそうでしょ。夢の話だからまあ、正確かどうかは問題ではないけど、そんなもんかなと思わせるのはさすが。
・語り手である男と、彼を捕えた大将との対峙シーンから、一転してそのままの語り口で遠くの女を描く。
・その視点の移動も大きいけど、よく読むとそこまでにも当事者としての語りというより解説挿入的な部分がけっこう入っている。
☆そんなわけで当事者目線で読むときも多いけど、ときどき第三者目線でやってみたりする。
[第六夜]
・「鎌倉時代とも思われる」ような場所に運慶がいる。木の高いところにいて「仁王を刻んでいる」らしい。「ところが見ているものは」「明治の人間」。
・そうしてもっぱら見物視線から運慶の様子を描ききるのかと思わせつつ、意外にも途中でその場とはお別れ。「急に自分も仁王が彫ってみたくなった」のだ。
・そんなわけで最後の場面では、「明治の木にはとうてい仁王は埋っていない」と悟る。悟るのは悟るでそれでいいのだが、その締めが「それで運慶が今日まで生きている理由もほぼ解った」。読者としても一瞬「解った」気になるのだが、よくよく考えると理屈は通ってない。
☆読み手としてはしかしだからこそ、どれだけ「解った」気にさせるかだよなと思ったりする。
[第七夜]
・舞台はさらにここまでの作品と毛色の違う場が舞台。船である。「けれどもどこへ行くんだか分らない」。
・終始、地の文は当事者スタンスで展開。そして「つまらないから死のうとさえ思って」いく。
・登場して何かを言う人の数は、全篇で一番多い。
・ただねー「」で括ってるセリフと、そうじゃないセリフとが混在しているのがちょっとひっかかるんだよねえ。
☆ひっかかるけど、まあセリフだろうと言うのは通常セリフ的に読んでいることが多いなあ。
☆これも最後の一文をどう聴かせるか。そこに至るまでに何を積み重ねるかが大きい篇だと思う。「どこへ行くんだか分らない」船に、それまでにどれだけリアリティを積み重ねるか。
[第八夜]
・一転、日常的な場(であったろう)、床屋が舞台。
・全体を通じて「鏡」に映る「窓の外を通る往来」を気にする当事者視線で描かれている。
・最後に「帳場格子」の「女」が見えるのだが、そこから急に「不思議」が立ち上がる。
・そして「金魚売」。
☆最後の一文で、この金魚売をどんな風情で「眺めている」ようにするか。その振り幅は多分、全篇中一番大きい。つまり一番捉えどころがない篇(笑)。
[第九夜]
・これまた一転して、今度は終始、第三者視線で描かれた篇。唯一、女性が主役のお話と言ってもいいだろう。
・ときどき地の文は主役から目を離し、あたりにある物を「面白い」などとも語ってしまう。
・そのくせそれは「夢の中で母から聞いた」話だって最後に締めるんだよね。この最終文とその前の文で二段落ちだよね。
☆クライマックスの「お百度参り」シーンには、主役のセリフは出てこない。まあだから第三者視線の地の文ながら、主役の心境をつい忍ばせたくなる。そうやってることが多いのだけど、もっと見守る側でいてもいいんだろうなあ。
[第十夜]
・全十篇中、唯一、笑いが出ることのある篇。まあ「くすっ」程度だけど。
・そして「第八夜」に登場した固有名詞の人物「庄太郎」が主役という、他の篇にはない特徴がある。
・とはいえ筆致は第三者視点。第三者だけど知り合いスタンスなのも特徴的か。
・ここに出てくる「女」は、しかしかなり怪しい。そしてこの篇ではセリフ的表現にまったく「」がない。
☆この「女」をどう造型するかってのが、読み語り的には一番の工夫どころかも。
●読者としては、第八夜に出てくる庄太郎の「連れ」の「女」と、この篇の「女」を同じと読むのも許されるだろう。しかしまあ、一貫して一人で読み語っても、そこを表現するってのはムリ。
と、こんなふうに全十篇を改めて解説風スタンスで見てきたら、あらあら、第一夜と第十夜、最初と最後の篇が共に、「女に何か要求されるお話」だったんですねえ。 続きを読む
2013年09月07日
「宮沢賢治*銀河鉄道を巡る冒険」を巡って2
音楽を楽譜だけで楽しめる人なんてレアでしょ。
聴くことや、自分で歌うことが楽しみ方でしょ。
けど、
小説なんかは
たいていは、文字を読んで楽しむことの方が主流で
自分で声に出して読むことはもちろん
人の声で読まれるのを聴くことすら
なかなか楽しみとして認識されてないのが現状じゃん。
まあ、詩や童話とか絵本あたりで
少しは読み聴きする楽しみ方が
あるように思えるくらいで。
その差を埋めていくには
何をどうしたら
いいのかなあ。
いやいや、ひとりじゃどうしようもないことだけど
音楽系の方々とコラボするときって
すごい親近感を覚えると同時に
日常活動の相違に目がくらむ。
その一方で
そんなハンパな場所にいる自分を
分け隔てなく受け入れてくれる
音楽家たちには
頭が下がる。えっと抽象的な意でなく
ほんとになんか、ありがとうという下がりかた。
ジャパニーズ・レベランス(爆)?
小松崎健さんは
まっつにとって
そんな方の代表格のひとり。
なんて言うのも畏れ多いくらい
もっとビッグな方ですけど。
で、話を戻すと
「宮沢賢治*銀河鉄道を巡る冒険」
この構成作品は
テキストを読むだけじゃ見えないことが
確かに声に載せると見えてくる。
健さんの音に支えられると聴こえてくる。
あ、普通の小説よりはるかに
音楽に近い
健さんとの合わせ方も
なんとなく、よりそれっぽい気がするのだ。
13.09.07
聴くことや、自分で歌うことが楽しみ方でしょ。
けど、
小説なんかは
たいていは、文字を読んで楽しむことの方が主流で
自分で声に出して読むことはもちろん
人の声で読まれるのを聴くことすら
なかなか楽しみとして認識されてないのが現状じゃん。
まあ、詩や童話とか絵本あたりで
少しは読み聴きする楽しみ方が
あるように思えるくらいで。
その差を埋めていくには
何をどうしたら
いいのかなあ。
いやいや、ひとりじゃどうしようもないことだけど
音楽系の方々とコラボするときって
すごい親近感を覚えると同時に
日常活動の相違に目がくらむ。
その一方で
そんなハンパな場所にいる自分を
分け隔てなく受け入れてくれる
音楽家たちには
頭が下がる。えっと抽象的な意でなく
ほんとになんか、ありがとうという下がりかた。
ジャパニーズ・レベランス(爆)?
小松崎健さんは
まっつにとって
そんな方の代表格のひとり。
なんて言うのも畏れ多いくらい
もっとビッグな方ですけど。
で、話を戻すと
「宮沢賢治*銀河鉄道を巡る冒険」
この構成作品は
テキストを読むだけじゃ見えないことが
確かに声に載せると見えてくる。
健さんの音に支えられると聴こえてくる。
あ、普通の小説よりはるかに
音楽に近い
健さんとの合わせ方も
なんとなく、よりそれっぽい気がするのだ。
13.09.07
2013年09月05日
「宮沢賢治*銀河鉄道を巡る冒険」を巡って1
言葉は、
特に作品として上梓された言葉は
完成された後、
変貌することは珍しい。
けれど誰しも経験しているだろう。
子どもの頃に読んだ童話を
大人になって読むと
ずいぶん違う印象を受けるものと。
読み手の変化が
変わらない言葉の印象を変える。
言葉にはそういう面もある。
読み語りという
文字表現をライブなものに変換する行為も
いわば、そういう言葉の可能性を
信じてのことだ。
今、読み聴く、それぞれの我々に
常に言葉は新しく異なる蓄積を携えて響いてくる。
3年前までの「福島」と
今の「福島」が
善し悪しにかかわらず、
異なって意識されるように。
同じようにそれはまた
作者自身の言葉への想いを知ることによっても
変化するだろう。
それもまたまた
読み手や聴き手のイメージ変化のひとつでもある。
この「宮沢賢治*銀河鉄道を巡る冒険」では
たくさんのイメージが交錯する
宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を主軸にしつつ
そこに登場する
「月」や「鳥」「リンゴ」
あるいは「別れ」や「幸い」「祈り」を
語る賢治自身の言葉が
挿入された構成だ。
それは原構成者・長岡登美子氏の
いわば賢治解析の一端と
自分には今は思えるものである。
実は、初演前、初めて
具体的な指示などなく
テキストとして
これを受け取ったとき
我々は途方にくれたのだった。
にもかかわらず、
声にしたとき、
そして健さんのハンマーダルシマーの音色にのせたとき、
そのことは、
いきなりしっかり響いてきたのだった。
「読み語り」への理解もある長岡氏の意思に
そうしてのっかって、
まっつは踊るのである。
いや、踊らないけど。読むのだけれど。
いやいや、実ははっきり
健さんの音と長岡氏の意思に
やっぱり踊らされるのだけれど(笑)。
そして、その響く先にいる皆さんこそが
この長岡氏による賢治のコトバ群の案内によって
それぞれの賢治像(ほとんど像を持たない人も含め)を
出発点に、「賢治銀河への冒険」に
誘われることになる。
時間的都合で、元の長岡氏構成テキストの
一部を割愛しているが、
その可能性は、いささかも減じないはずだ。
13.09.05 続きを読む
特に作品として上梓された言葉は
完成された後、
変貌することは珍しい。
けれど誰しも経験しているだろう。
子どもの頃に読んだ童話を
大人になって読むと
ずいぶん違う印象を受けるものと。
読み手の変化が
変わらない言葉の印象を変える。
言葉にはそういう面もある。
読み語りという
文字表現をライブなものに変換する行為も
いわば、そういう言葉の可能性を
信じてのことだ。
今、読み聴く、それぞれの我々に
常に言葉は新しく異なる蓄積を携えて響いてくる。
3年前までの「福島」と
今の「福島」が
善し悪しにかかわらず、
異なって意識されるように。
同じようにそれはまた
作者自身の言葉への想いを知ることによっても
変化するだろう。
それもまたまた
読み手や聴き手のイメージ変化のひとつでもある。
この「宮沢賢治*銀河鉄道を巡る冒険」では
たくさんのイメージが交錯する
宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を主軸にしつつ
そこに登場する
「月」や「鳥」「リンゴ」
あるいは「別れ」や「幸い」「祈り」を
語る賢治自身の言葉が
挿入された構成だ。
それは原構成者・長岡登美子氏の
いわば賢治解析の一端と
自分には今は思えるものである。
実は、初演前、初めて
具体的な指示などなく
テキストとして
これを受け取ったとき
我々は途方にくれたのだった。
にもかかわらず、
声にしたとき、
そして健さんのハンマーダルシマーの音色にのせたとき、
そのことは、
いきなりしっかり響いてきたのだった。
「読み語り」への理解もある長岡氏の意思に
そうしてのっかって、
まっつは踊るのである。
いや、踊らないけど。読むのだけれど。
いやいや、実ははっきり
健さんの音と長岡氏の意思に
やっぱり踊らされるのだけれど(笑)。
そして、その響く先にいる皆さんこそが
この長岡氏による賢治のコトバ群の案内によって
それぞれの賢治像(ほとんど像を持たない人も含め)を
出発点に、「賢治銀河への冒険」に
誘われることになる。
時間的都合で、元の長岡氏構成テキストの
一部を割愛しているが、
その可能性は、いささかも減じないはずだ。
13.09.05 続きを読む



